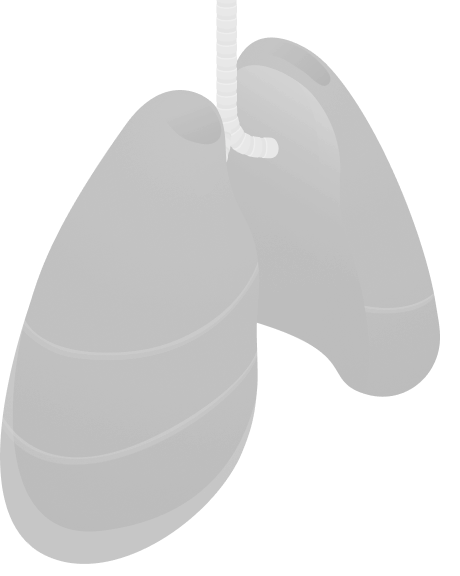肺がんの種類を組織型に分けた時の分類で、
小細胞肺がん以外の腺がん、扁平上皮がん、大細胞がんなど。
ステージ0
ステージ0の非小細胞肺がんとは
上皮内がんと呼ばれるがんになります。
5年生存率は99.3%と100%ではないので、必ず転移がないとは言い切れないがんですが、ほとんど転移の可能性がないがんになります。なので、手術やPDT、放射線治療などでほとんど完治が見込めるがんになります。
向いている治療
再発の可能性が低いので追加の治療の必要性はほとんど感じないですが、他臓器への再発が起きた場合はステージ4になるので、仮に行うのであれば、核酸医薬の治療になります。
ステージ1
ステージ1の非小細胞肺がんとは
リンパ節転移もなく、他臓器への転移もなく、原発部位(肺にあるがん)の大きさが4センチまでのがんになります。基本的に手術や放射線が可能ながんです。中心部にありかつ小さいがんであれば、PDT(光線力学的療法)という治療も標準治療で行うことが可能です。
非小細胞肺がんはステージ1でも10年生存率が62.9%と再発の可能性が極めて高いがんなので、原発部位のがんの大きさが2センチ以上あると、追加の再発予防の為の抗がん剤が検討されます。使う抗がん剤は分子標的薬(免疫チェックポイント阻害剤を含む)などのタンパク質をターゲットとした分子標的薬などの抗がん剤は再発予防には向かないので、肺がんで標準的に調べる遺伝子(EGFR,ALKなど)の検査の結果を用いた抗がん剤は再発予防では使用されず、細胞障害性の抗がん剤を使うことになります。他臓器への再発が起きるとステージ4となります。
ステージ1における非小細胞肺がんの治療における自由診療の考え方
ステージ1の非小細胞肺がんは転移がないがんなので、肺にあるがんを手術や放射線などで取り除く治療になります。
ただ、転移がないというのはあくまでもPET-CTなどの画像検査で見えるレベルの転移がないというだけで、PET-CTに映らないレベルのがんの転移は有るかもしれないと考えます。なので、手術や放射線の後、「5年待ちましょう」ということになります。それは画像に映らないレベルのがんの転移は有るかもしれないけど、その大きさのがんを見つけるための検査がないので、がんが大きくなるのを5年待ちましょうということです。5年経っても大きくなるがんがどこからも出なければ、「5年前に完治していました」ということを5年後に教えてくれる話になり、がん治療が終了します。ただ、非小細胞肺がんのステージ1の10年生存率が62.9%であることから、手術後に再発予防の抗がん剤をしても少なくとも4割近くのがんが再発するということになります。言い換えれば、4割ぐらいのがんは手術の前に既に転移があったということになります(手術の前からステージ4だった)。なので、手術の前後に全身治療を抗がん剤の他に自由診療でさらに追加することが大切になります。追加の治療はタンパク質をターゲットにした治療よりも、すべてのがんをターゲットにした治療の方が向いていると考えられます。
向いている治療
CASE 1
詳細を見る
手術で見えているがんを取り除くことができても、体内のどこかにごく小さながん細胞が残っている可能性があります。再発予防では、この「どこに潜んでいるか分からないがん」に対して働きかけられる全身治療が重要です。
核酸医薬は、がんの増殖に関わる遺伝子や異常なたんぱく質の働きを抑えることで、こうした残存の可能性があるがん細胞にも幅広くアプローチでき、副作用が比較的少ない点が特徴です。そのため、再発予防の段階で用いられることが多い治療のひとつです。
また、p53の働きが弱いタイプのがんは、抗がん剤や放射線に耐性を示すことがあります。抗がん剤治療の前後や途中に核酸医薬を併用することで、核酸医薬そのものの作用に加え、抗がん剤の効果が高まる可能性も報告されています。
さらに、非小細胞肺がんではがんのタイプごとに特徴が異なり、たとえば肺腺がんではKRAS、扁平上皮がんではPIK3CAなど、過剰に働く遺伝子が異なる傾向が知られています。がん中央クリニックグループでは、それぞれのがんの性質に合わせて、KRAS siRNA、MDM2 siRNA、CDK4 siRNA、ガンキリン(PMSD10)siRNA、miR-34a mimic など、対象となる遺伝子の働きを抑える核酸医薬を組み合わせた治療を行っています。
「アプタマー核酸医薬」 詳細ページ
「RNA干渉 核酸医薬」 詳細ページ
「miRNA mimic 核酸医薬」 詳細ページ
CASE 2
詳細を見る
腫瘍溶解ウイルス療法の効果の高さは注目されてきています。保険ではウイルス療法としてデリタクトが脳腫瘍で認可されましたが局所的な治療になります。がん中央クリニックグループで行っている腫瘍溶解ウイルス療法は点滴で行うことが出来、全身に作用し、見えないがんにも効果を発揮し、ウイルスががん細胞にのみ感染することで普通細胞には害がない状態でがんを死滅に追い込みます。日本の大きな病院での治験も予定されており、今後ますます発展が期待されている治療方法になります。
ステージ2
ステージ2の非小細胞肺がんとは
リンパ節転移があり、さらに比較的そこまで大きくないがんが肺にあり、他臓器への転移がないがん、もしくはリンパ節転移や他臓器への転移はないが大きながんや同じ肺葉内で離れたところにもう一つがんがある、浸潤が広がっている状態のがんになります。基本的に手術や放射線が可能ながんです。
非小細胞肺がんはステージ2でも10年生存率が28.7%と再発の可能性が極めて高いがんなので、手術前に抗がん剤と手術後にも抗がん剤を行うことになります。使う抗がん剤は分子標的薬(免疫チェックポイント阻害剤も含む)などのタンパク質をターゲットとした抗がん剤は再発予防には向かないので、肺がんで標準的に調べる遺伝子(EGFR,ALKなど)の検査の結果を用いた抗がん剤は再発予防では使用されず、細胞障害性の抗がん剤を使うことになります。他臓器への再発が起きるとステージ4となります。
ステージ2における非小細胞肺がんの治療における自由診療の考え方
ステージ2の非小細胞肺がんは他臓器への転移がないがんなので、肺にあるがんと転移先のリンパ節を手術や放射線などで取り除く治療になります。ただ、他臓器転移がないというのはあくまでもPET-CTなどの画像検査で見えるレベルの転移がないというだけで、PET-CTに映らないレベルのがんの転移は高い確率であると考えます。なので、手術や放射線の後、「5年待ちましょう」ということになります。それは画像に映らないレベルのがんの転移は有るかもしれないけど、その大きさのがんを見つけるための検査がないので、がんが大きくなるのを5年待ちましょうということです。5年経っても大きくなるがんがどこからも出なければ、「5年前に完治していました」ということを5年後に教えてくれる話になり、がん治療が終了します。ただ、非小細胞肺がんのステージ2の10年生存率が28.7%であることから、手術後に再発予防の抗がん剤をしても少なくとも7割以上のがんが再発するということになります。言い換えれば、7割ぐらいのがんは手術の前に既に転移があったということになります(手術の前からステージ4だった)。なので、手術の前後に全身治療を抗がん剤の他に自由診療でさらに追加することが大切になります。追加の治療はタンパク質をターゲットにした治療よりも、すべてのがんをターゲットにした治療の方が向いていると考えられます。
向いている治療
CASE 1
詳細を見る
手術で見えているがんを取り除くことができても、体内のどこかにごく小さながん細胞が残っている可能性があります。再発予防では、この「どこに潜んでいるか分からないがん」に対して働きかけられる全身治療が重要です。
核酸医薬は、がんの増殖に関わる遺伝子や異常なたんぱく質の働きを抑えることで、こうした残存の可能性があるがん細胞にも幅広くアプローチでき、副作用が比較的少ない点が特徴です。そのため、再発予防の段階で用いられることが多い治療のひとつです。
また、p53の働きが弱いタイプのがんは、抗がん剤や放射線に耐性を示すことがあります。抗がん剤治療の前後や途中に核酸医薬を併用することで、核酸医薬そのものの作用に加え、抗がん剤の効果が高まる可能性も報告されています。
さらに、非小細胞肺がんではがんのタイプごとに特徴が異なり、たとえば肺腺がんではKRAS、扁平上皮がんではPIK3CAなど、過剰に働く遺伝子が異なる傾向が知られています。がん中央クリニックグループでは、それぞれのがんの性質に合わせて、KRAS siRNA、MDM2 siRNA、CDK4 siRNA、ガンキリン(PMSD10)siRNA、miR-34a mimic など、対象となる遺伝子の働きを抑える核酸医薬を組み合わせた治療を行っています。
「アプタマー核酸医薬」 詳細ページ
「RNA干渉 核酸医薬」 詳細ページ
「miRNA mimic 核酸医薬」 詳細ページ
CASE 2
詳細を見る
腫瘍溶解ウイルス療法の効果の高さは注目されてきています。保険ではウイルス療法としてデリタクトが脳腫瘍で認可されましたが局所的な治療になります。がん中央クリニックグループで行っている腫瘍溶解ウイルス療法は点滴で行うことが出来、全身に作用し、見えないがんにも効果を発揮し、ウイルスががん細胞にのみ感染することで普通細胞には害がない状態でがんを死滅に追い込みます。日本の大きな病院での治験も予定されており、今後ますます発展が期待されている治療方法になります。
ステージ3
ステージ3の非小細胞肺がんとは
離れた場所へのリンパ節転移があり、さらに比較的そこまで大きくないがんが肺にあり、他臓器への転移がないがんかリンパ節転移や他臓器への転移はないが大きながんや同じ側だけど違う肺葉内にもう一つがんがある状態、浸潤が広がっているがんになります。基本的に手術が難しいがんの状態です(手術が可能な場合もある→ステージ2の非小細胞肺がんの詳細を参照)。手術が無理な場合は化学放射線療法になります。化学放射線療法も無理な場合は、ステージ4の場合と同等な抗がん剤治療になります(ステージ4を参照)。
非小細胞肺がんはステージ3だと10年生存率が12.8%とほぼ再発が起こってしまうがんになります。化学放射線療法で使う抗がん剤は分子標的薬などのタンパク質をターゲットとした分子標的薬や免疫チェックポイント阻害剤ではなく、細胞障害性の抗がん剤を使うことになります。他臓器への再発が起きるとステージ4となります。
※ステージ3における非小細胞肺がんの治療における自由診療の考え方
ステージ3の非小細胞肺がんは他臓器への転移がないがんなので、化学放射線療法で一旦はがんが消えます。ただ、他臓器転移がないというのはあくまでもPET-CTなどの画像検査で見えるレベルの転移がないというだけで、PET-CTに映らないレベルのがんの転移は高い確率で起こっていると考えます。化学放射線療法の後、見えてるがんがないので「5年待ちましょう」ということになります。それは画像に映らないレベルのがんの転移は高い確率で有るけど、その大きさのがんを見つけるための検査がないので、がんが大きくなるのを5年待ちましょうということです。5年経っても大きくなるがんがどこからも出なければ、「5年前に完治していました」ということを5年後に教えてくれる話になり、がん治療が終了します。ただ、非小細胞肺がんのステージ3の10年生存率が12.8%であることから、9割近いがんが再発するということになります。言い換えれば、ステージ3の非小細胞肺がんの9割ぐらいのがんは化学放射線療法の前に既に転移があったということになります(放射線化学療法の前からステージ4だった)。なので、化学放射線療法の前後に全身治療を自由診療でさらに追加することが大切になります。追加の治療はタンパク質をターゲットにした治療よりも、すべてのがんをターゲットにした治療の方が向いていると考えられます。
向いている治療
CASE 1
詳細を見る
手術で見えているがんを取り除くことができても、体内のどこかにごく小さながん細胞が残っている可能性があります。再発予防では、この「どこに潜んでいるか分からないがん」に対して働きかけられる全身治療が重要です。
核酸医薬は、がんの増殖に関わる遺伝子や異常なたんぱく質の働きを抑えることで、こうした残存の可能性があるがん細胞にも幅広くアプローチでき、副作用が比較的少ない点が特徴です。そのため、再発予防の段階で用いられることが多い治療のひとつです。
また、p53の働きが弱いタイプのがんは、抗がん剤や放射線に耐性を示すことがあります。抗がん剤治療の前後や途中に核酸医薬を併用することで、核酸医薬そのものの作用に加え、抗がん剤の効果が高まる可能性も報告されています。
さらに、非小細胞肺がんではがんのタイプごとに特徴が異なり、たとえば肺腺がんではKRAS、扁平上皮がんではPIK3CAなど、過剰に働く遺伝子が異なる傾向が知られています。がん中央クリニックグループでは、それぞれのがんの性質に合わせて、KRAS siRNA、MDM2 siRNA、CDK4 siRNA、ガンキリン(PMSD10)siRNA、miR-34a mimic など、対象となる遺伝子の働きを抑える核酸医薬を組み合わせた治療を行っています。
「アプタマー核酸医薬」 詳細ページ
「RNA干渉 核酸医薬」 詳細ページ
「miRNA mimic 核酸医薬」 詳細ページ
CASE 2
詳細を見る
腫瘍溶解ウイルス療法の効果の高さは注目されてきています。保険ではウイルス療法としてデリタクトが脳腫瘍で認可されましたが局所的な治療になります。がん中央クリニックグループで行っている腫瘍溶解ウイルス療法は点滴で行うことが出来、全身に作用し、見えないがんにも効果を発揮し、ウイルスががん細胞にのみ感染することで普通細胞には害がない状態でがんを死滅に追い込みます。日本の大きな病院での治験も予定されており、今後ますます発展が期待されている治療方法になります。
ステージ4
ステージ4の非小細胞肺がんとは
他臓器への転移がある状態、もしくは反対側の肺に転移があるがんになります。基本的に手術、放射線が出来ないがんになります(重粒子線、陽子線、サイバーナイフなども含む)。1つでも転移があると見えてるがん以外にも全身にがんがあると考えるので全身治療が基本になります。肺がんは認可されている分子標的薬が多いので、決められた数の遺伝子検査を病理検査で行い、遺伝子の変異に合う抗がん剤(分子標的薬、免疫チェックポイント阻害剤)を優先して使います。合う分子標的薬や免疫チェックポイント阻害剤がない場合や分子標的薬や免疫チェックポイント阻害剤を使い切った場合は、細胞障害性の抗がん剤を使っていき、それでも使える抗がん剤がなくなると遺伝子パネル検査を使ったゲノム医療へと進みます(2種類程度の抗がん剤を使った後に進む場合もある)。ゲノム医療とは、遺伝子検査をして使える抗がん剤(分子標的薬)をさがして使うという取り組みになります。
非小細胞肺がんはステージ4だと10年生存率が2.3%なので、標準治療だけの治療では極めて厳しいステージになります。1日でも早い段階から自由診療で何か治療をプラスして考えることが良い結果を産むことになるとがん中央クリニックグループでは考えています。
ステージ4における非小細胞肺がんの治療における自由診療の考え方
非小細胞肺がんのステージ4で使う分子標的薬や免疫チェックポイント阻害剤と言った抗がん剤は極めて優秀なものが多いのが特徴です。ただ、その極めて優秀な抗がん剤をつかったとしても、10年生存率が2.3%と大変厳しい結果になっているので、そこに何かプラスで治療を考えなくてはいけないがんだと考えています。がん中央クリニックグループで行っている治療は、他クリニックでは見ることが出来ないレベルの新しい治療を数多く揃えています。
向いている治療
CASE 1
詳細を見る
非小細胞肺がんでは、がん細胞の増殖を抑える役割を持つp53の働きが弱くなっていたり、変化しているケースが多く見られます。このようなタイプのがんは、抗がん剤や放射線に耐性を示すことがあり、治療が進むにつれて効果が得られにくくなることがあります。
核酸医薬は、がんの増殖に関わる遺伝子や異常なたんぱく質の働きを調整することで、がん細胞に直接アプローチできる治療です。抗がん剤治療の前後や治療の途中に併用することで、核酸医薬そのものの働きに加えて、抗がん剤の効果を補う可能性も報告されています。特に肺がんは抗がん剤の選択肢が多いため、組み合わせる意義は大きいと考えられています。
また、非小細胞肺がんは「同じ肺がん」であっても種類によって特徴が大きく異なります。
たとえば「肺腺がんでは KRAS が過剰に働いている例が多い」「扁平上皮がんでは PIK3CA が過剰に働いている例が多い」など、がんが持つ性質に応じて狙うべき標的が変わります。
がん中央クリニックグループでは、こうした特徴に合わせてKRAS siRNA、MDM2 siRNA、CDK4 siRNA、ガンキリン(PMSD10)siRNA、miR-34a mimic など複数の核酸医薬を組み合わせ、がんの性質に沿った治療設計を行っています。
そのため、抗がん剤開始前、途中でも、がん細胞の性質に応じた新たな核酸医薬でアプローチする選択肢を検討できることがあります。
「アプタマー核酸医薬」 詳細ページ
「RNA干渉 核酸医薬」 詳細ページ
「miRNA mimic 核酸医薬」 詳細ページ
詳細を見る
抗HER2抗体がアメリカのFDAで全がん種で承認されたことが2025年1月に話題になりました。また、HER2陰性でも効果があることが実証され、日本でもHER2低発現やさらに低い発現の超低発現でも乳がんで抗HER2抗体が認可され、全がん種でHER2濃度関係なく効果がある可能性が高くなってきました。どのがんでも初めに抗HER2抗体の治療をするということが大切なぐらい重要度が増してきている治療と考えられます。この分子標的ワクチン療法はアメリカの治験の結果が非常に優れていた為、無理にお願いをして契約の元、日本で治療が可能になった治療になります。エビデンスレベルは非常に高く、どのがん種においても高い効果が期待出来ます。2種類の抗HER2ワクチンを体内で作り出すことが出来ることと、長く効果が持続することが特徴で、アメリカでは効果の持続が7年に及ぶ患者様まで現れています。副作用がほとんどなく、効果が高く、さらに効果が長く続くことから非常に優れた治療方法であると考えています。
CASE 2
詳細を見る
非小細胞肺がんでは、がん細胞の増殖を抑える役割を持つp53の働きが弱くなっていたり、変化しているケースが多く見られます。このようなタイプのがんは、抗がん剤や放射線に耐性を示すことがあり、治療が進むにつれて効果が得られにくくなることがあります。
核酸医薬は、がんの増殖に関わる遺伝子や異常なたんぱく質の働きを調整することで、がん細胞に直接アプローチできる治療です。抗がん剤治療の前後や治療の途中に併用することで、核酸医薬そのものの働きに加えて、抗がん剤の効果を補う可能性も報告されています。特に肺がんは抗がん剤の選択肢が多いため、組み合わせる意義は大きいと考えられています。
また、非小細胞肺がんは「同じ肺がん」であっても種類によって特徴が大きく異なります。
たとえば「肺腺がんでは KRAS が過剰に働いている例が多い」「扁平上皮がんでは PIK3CA が過剰に働いている例が多い」など、がんが持つ性質に応じて狙うべき標的が変わります。
がん中央クリニックグループでは、こうした特徴に合わせてKRAS siRNA、MDM2 siRNA、CDK4 siRNA、ガンキリン(PMSD10)siRNA、miR-34a mimic など複数の核酸医薬を組み合わせ、がんの性質に沿った治療設計を行っています。
そのため、抗がん剤途中で免疫チェックポイント阻害剤終了後でも、がん細胞の性質に応じた新たな核酸医薬でアプローチする選択肢を検討できることがあります。
「アプタマー核酸医薬」 詳細ページ
「RNA干渉 核酸医薬」 詳細ページ
「miRNA mimic 核酸医薬」 詳細ページ
CASE 3
詳細を見る
抗HER2抗体がアメリカのFDAで全がん種で承認されたことが2025年1月に話題になりました。また、HER2陰性でも効果があることが実証され、日本でもHER2低発現やさらに低い発現の超低発現でも乳がんで抗HER2抗体が認可され、全がん種でHER2濃度関係なく効果がある可能性が高くなってきました。どのがんでも初めに抗HER2抗体の治療をするということが大切なぐらい重要度が増してきている治療と考えられます。この分子標的ワクチン療法はアメリカの治験の結果が非常に優れていた為、無理にお願いをして契約の元、日本で治療が可能になった治療になります。エビデンスレベルは非常に高く、どのがん種においても高い効果が期待出来ます。2種類の抗HER2ワクチンを体内で作り出すことが出来ることと、長く効果が持続することが特徴で、アメリカでは効果の持続が7年に及ぶ患者様まで現れています。副作用がほとんどなく、効果が高く、さらに効果が長く続くことから非常に優れた治療方法であると考えています。
詳細を見る
腫瘍溶解ウイルス療法の効果の高さは注目されてきています。保険ではウイルス療法としてデリタクトが脳腫瘍で認可されましたが局所的な治療になります。がん中央クリニックグループで行っている腫瘍溶解ウイルス療法は点滴で行うことが出来、全身に作用し、見えないがんにも効果を発揮し、ウイルスががん細胞にのみ感染することで普通細胞には害がない状態でがんを死滅に追い込みます。日本の大きな病院での治験も予定されており、今後ますます発展が期待されている治療方法になります。
詳細を見る
非小細胞肺がんでは、がん細胞の増殖を抑える役割を持つp53の働きが弱くなっていたり、変化しているケースが多く見られます。このようなタイプのがんは、抗がん剤や放射線に耐性を示すことがあり、治療が進むにつれて効果が得られにくくなることがあります。
核酸医薬は、がんの増殖に関わる遺伝子や異常なたんぱく質の働きを調整することで、がん細胞に直接アプローチできる治療です。抗がん剤治療の前後や治療の途中に併用することで、核酸医薬そのものの働きに加えて、抗がん剤の効果を補う可能性も報告されています。特に肺がんは抗がん剤の選択肢が多いため、組み合わせる意義は大きいと考えられています。
また、非小細胞肺がんは「同じ肺がん」であっても種類によって特徴が大きく異なります。
たとえば「肺腺がんでは KRAS が過剰に働いている例が多い」「扁平上皮がんでは PIK3CA が過剰に働いている例が多い」など、がんが持つ性質に応じて狙うべき標的が変わります。
がん中央クリニックグループでは、こうした特徴に合わせてKRAS siRNA、MDM2 siRNA、CDK4 siRNA、ガンキリン(PMSD10)siRNA、miR-34a mimic など複数の核酸医薬を組み合わせ、がんの性質に沿った治療設計を行っています。
そのため、治療方法がないと言われた場合でも、がん細胞の性質に応じた新たな核酸医薬でアプローチする選択肢を検討できることがあります。
「アプタマー核酸医薬」 詳細ページ
「RNA干渉 核酸医薬」 詳細ページ
「miRNA mimic 核酸医薬」 詳細ページ
CASE 4
詳細を見る
ヨードを使った治療は数十年の歴史があり、がん患者様の定番の治療方法となっています。安全性が高く服用による治療の為、入院中でも出来る治療として多くのがん患者様が治療に使っています。イオン化したコロイドヨードよりも分子型の有機ヨードはがん細胞への浸透は高いのと、がん治療に限らず殺菌作用、抗ウイルス作用が高い為、多くの用途で良く使われています。
詳細を見る
分子型有機ヨードと同様にヨードを使った治療になります。甲状腺への取り込みはイオン型のコロイドヨードの方が能力としては高い為、昔からよく使われていた治療になります。
胸膜播種がある場合
胸膜播種がある場合、以下の治療を推奨しています。
腹水への局所注入
詳細を見る
分子型の有機ヨードは細胞への浸透が高い為、直接がん細胞に触れられる形で投与することがさらに高い効果が期待されています。がん細胞を殺す力が強いため、腹水がたまらなくなるようにすることはもちろん、お腹から吸収されて全身のがんにも効果が期待されるものになります。
光免疫療法の腹部への照射
詳細を見る
がん中央クリニックグループの光照射は面で当てる光照射の機械を使っています。光の強さは光源の数に比例するので、面で当てることで最大限の光の強さが期待出来ます。また、腹膜播種はCTなどに映っていなくてもお腹いっぱいに広がっていることが予想されるがんなので、面で光をあてることが必要になります。LEDを使い、さらに熱を持つ波長体をカットすることで強い光を当てることを可能にした機械になります。パルス照射で深部まであてることが出来るので、腹膜播種のような広く広がっているがんにはさらに効果が期待出来る様になっています。